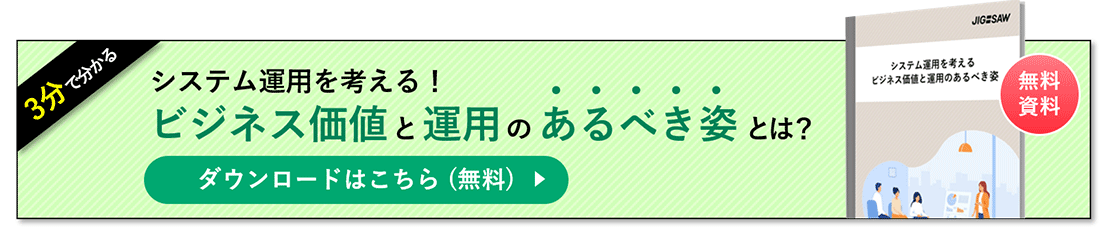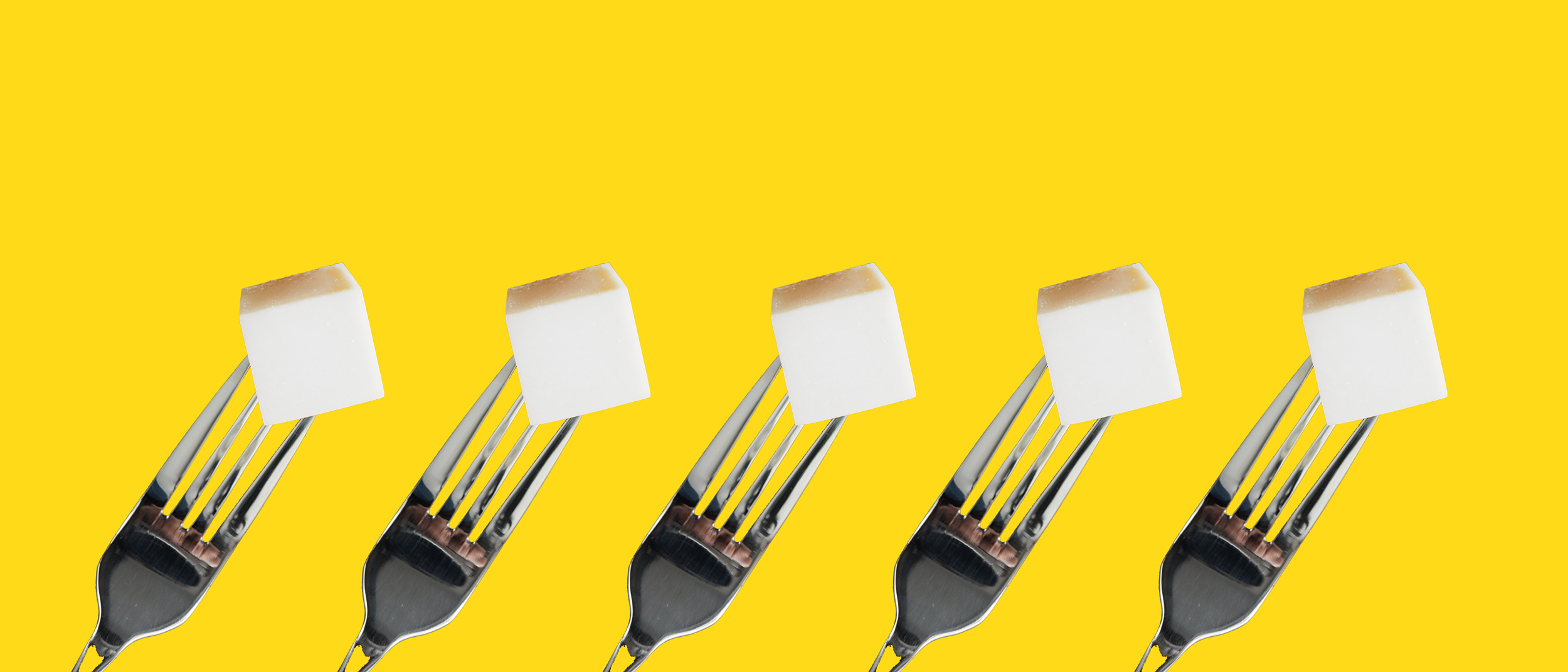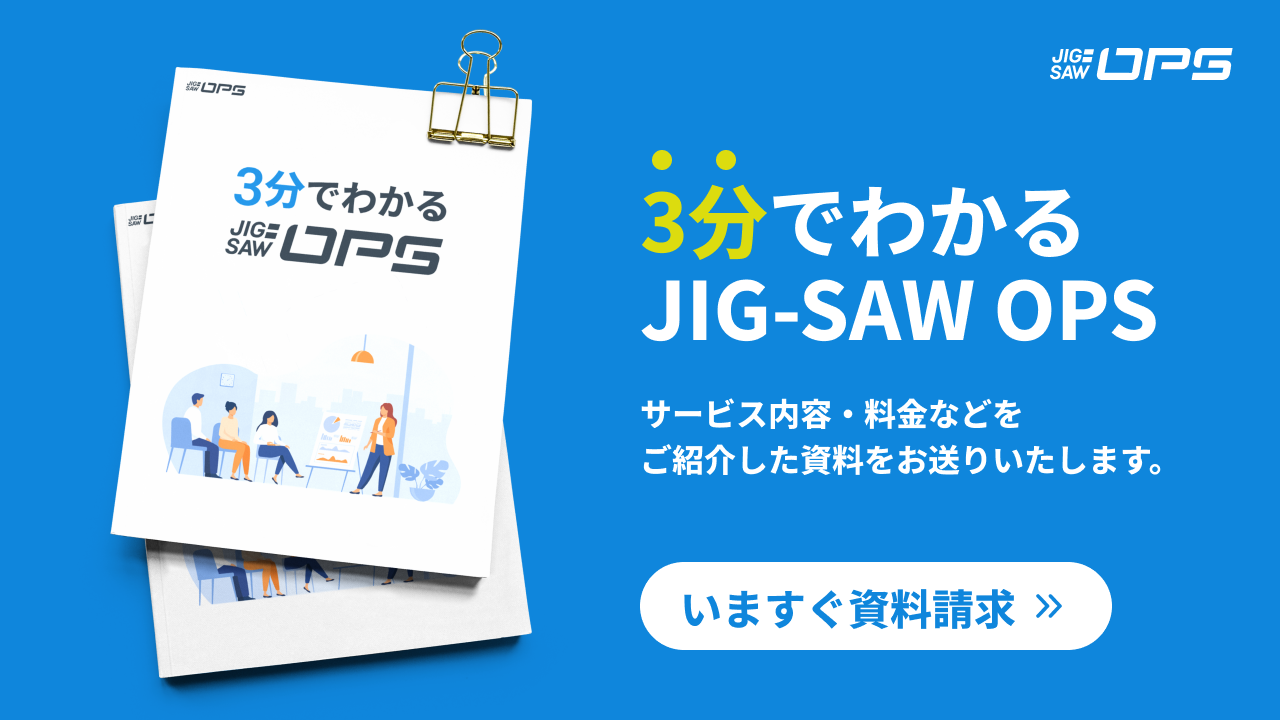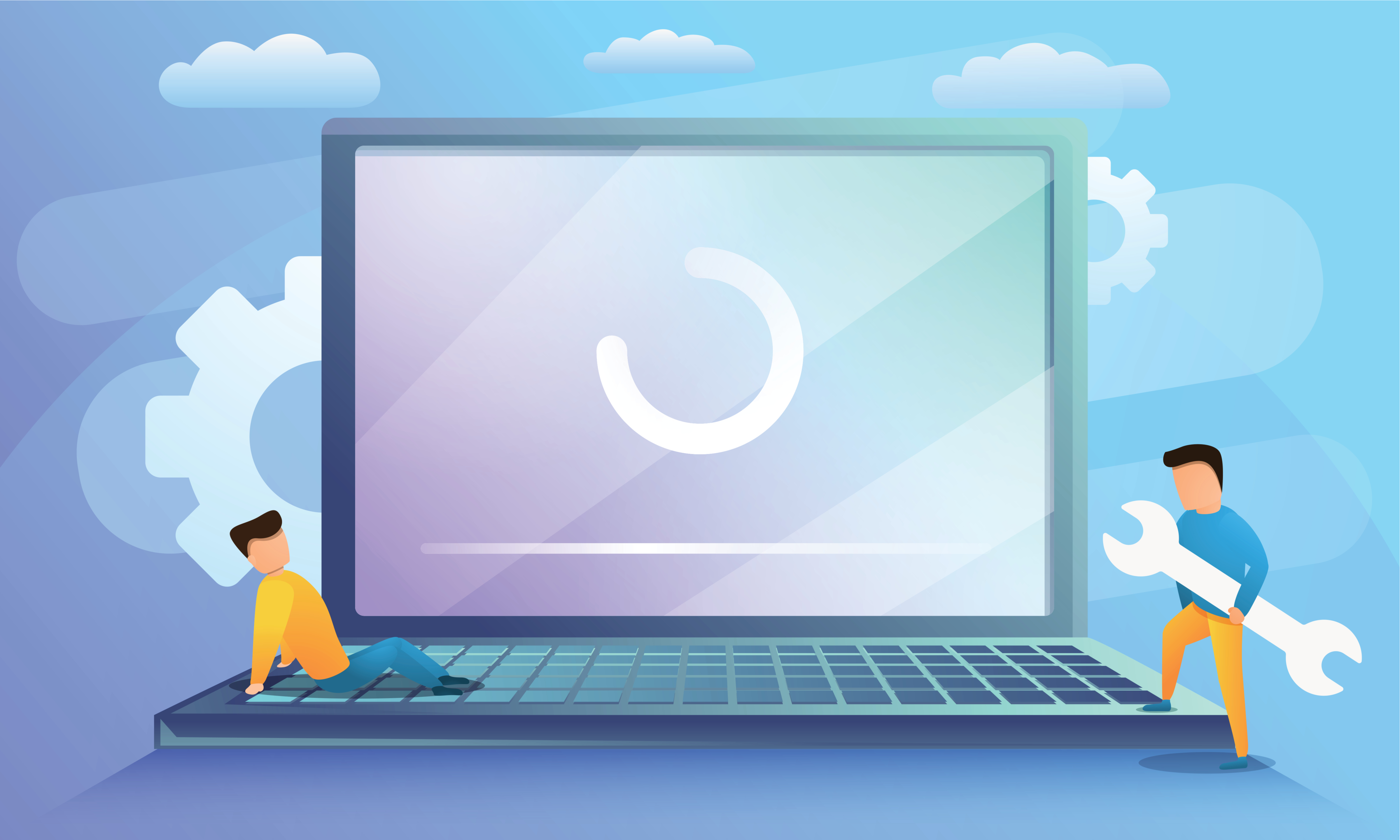
CentOS おすすめの移行先とは?
2022年以降の日本のOSトレンドを予測!
2021.08.02
CentOSのサポート終了に伴い、どのOSに移行するかお悩みの方に向けて、移行先の候補となるOSを比較しつつ、2022年以降の日本のOSトレンド予測をご紹介します。
CentOS、移行先の選定問題
ITシステムの運用者、もしくは開発者の皆様は CentOSからの移行先OSの選定で悩んでいる方も多いと思います。
CentOS Streamは、Red Hat Enterprise Linux(以下、RHEL)のダウンストリームの位置づけであったCentOSとは異なります。
どう異なるかというと、CentOS Stream はRHELのアップストリームになり、検証的なディストリビューションとなります。これを機会に、別のOSへの移行を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、移行先の候補となるOSを比較しつつ、2022年以降の日本のOSトレンドを予測します!
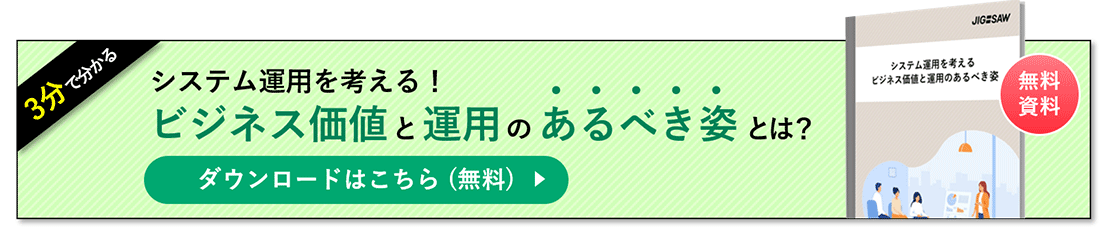
CentOS Streamの問題点とは?
CentOSからの移行先候補のOSについて述べる前に、まずはCentOS Streamの問題点について触れたいと思います。
CentOS Streamの問題点は、RHELのアップストリームとなった点です。
CentOSは、RHELのダウンストリームとして、安定性のあるRHEL互換のOSとされていました。 このため、CentOSは安定稼働しているRHELに対して商標や商用パッケージの削除や置き換え等を行って構築されるディストリビューションとなります。
一方で、CentOS Streamは、RHELのアップストリームとして位置づけられています。
したがって、完全に検証される前の“ソースパッケージ品質テスト”を行うディストリビューションの側面を持っています。
また、更新の際に不具合が発生する可能性もあります。
CentOSの高い安定性がOS選定の主軸となっていることもあり、CentOS Streamの持つわずかな不安定性は稼働させるシステムによっては大きな問題となってきます。
CentOSの移行先、4つの候補
CentOS Streamの問題点をご理解いただいたところで、次に上記問題を解決する4つの選択肢についてご説明します。
選択肢としては、以下が挙げられます。
・RHELに乗り換える(有償)
・CentOS Streamに乗り換える(無償)
・CentOS 7 を利用する(無償)
・異なるOSに乗り換える(無償)
いずれも一長一短があります。
上記のうち「RHELへ乗り換える(有償)」はCentOSを利用しているため、商用パッケージ等の利用目途は無いことが多いでしょう。さらに、有償であるという点から選択肢として候補に挙がりにくいと思います。
また、「CentOS 7を利用する(無償)」選択はあくまでも一時的な対応策であるため、こちらもあまり推奨できません。したがって、基本的には「CentOS Streamに乗り換える」もしくは「異なるOSに乗り換える」の2択になることがほとんどでしょう。
今回は、「異なるOSに乗り換える(無償)」ことを前提として、移行先候補のOS比較やトレンド予測を行っていきます。
移行先候補のOS比較とトレンド予測
移行先候補のOS比較
CentOSとは異なるOSに乗り換える場合、移行先OSの選定が必要となってきます。
移行先OSの候補としては、以下のOSが考えられます。
・AlmaLinux
・Rockey Linux
・Oracle Linux
・Ubuntu
AlmaLinux
AlmaLinuxは、CentOS派生のホスティング事業者向けディストリビューションであるCloudLinuxの開発元が立ち上げたOSです。
CloudLinuxがRHELからフォークして開発されているため、開発元がノウハウを持っている点は良いですね。使用料は無料で、互換性はRHELと1対1のバイナリ互換となっています。
また、EOL(End of Life)はRHEL 8系と同じ2029年5月31日です。
基本的にはコミュニティ主導で開発されるとのことですが、実際にはCloudLinux社が主導するのではないか、と予想しています。
Rockey Linux
Rockey Linuxは、CentOSの元開発者が発表したOSとです。こちらもAlmaLinuxと同様に使用料は無料となっており、互換性はRHELとバグまで100%一致するように設計されています。
また、EOLはRHEL 8系と同じ2029年5月31日です。このOSはコミュニティ主導での開発になるとのことで、突発的な変更や方針転換が起きにくい点がメリットだと言えるでしょう。
Oracle Linux
Oracle Linuxは、Oracle社提供のディストリビューションです。RHELをリビルドしたもので、2つあるカーネルのうち、Red Hat Compatible Kernel(以下、RHCK)はRHELと完全に互換性を持つとされていますが、Oracle製品を利用するためのチューニングが含まれています。
こちらのOSも使用料は無料であり、EOLは2029年7月となっています。
また、AlmaLinuxやRocky Linuxとは異なり、リリースしてから期間が経過しているため、信頼性が高いOSと言えます。
ただ、Oracle Linuxを使用している方をあまり見ない傾向にあるため、世間的にナレッジが少ないことが懸念点と言えるでしょう。
Ubuntu
Ubuntuは、Debian GNU/LinuxをベースとしたOSです。使用料は無料で、EOLはLong Term Support版(以下、LTS版)であればリリースから5年間サポートされます。
また、安全保守延長期間を合わせると、サポート期間は合計10年となります。
Ubuntuは海外でのプロダクション環境でトップシェアの実績があるため、世間的にナレッジが多くあります。
ただし、Debian系のディストリビューションとなるため、RHELとの互換性はありません。また、パッケージ管理や各種設定がCentOSと一部異なるため、移行のハードルが高い点がデメリットであると言えるでしょう。
2022年以降の日本のOSトレンド予測
2022年以降の日本では、Rocky Linuxがトレンドになると予測されます。次にAlmaLinux、その次にUbuntuがトレンドになる可能性が高いでしょう。
理由としては、RHELのダウンストリームで互換性があるためです。
安定性を重視する上で、RHELのダウンストリームであることは必須と考えます。RHELと互換性があるため、既存環境で動作しているシステムへの影響を気にする必要がない点も、非常に大きなメリットです。
また、開発がコミュニティ主体であることも理由のひとつです。今回のCentOSのサポート終了を踏まえて、企業主体の開発だと「急な方針転換の可能性があるのではないか」と懸念されるユーザは少なくないでしょう。このため、コミュニティ主体での開発体制が好まれるのではないかと考えています。
終わりに
今回は、移行先候補となるOSを比較しつつ、2022年以降の日本のOSトレンド予測をご紹介しました。
著者の予測としては、CentOSとの互換性が非常に高く、コミュニティ主体の開発体制であるため、Rocky Linuxがトレンドになってくると考えています。
ただし、どのOSも一長一短があるものとなっていますので、実際のシステム要件と照らし合わせて、移行先をご検討してみてはいかがでしょうか。